
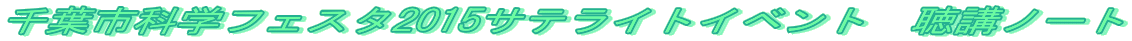
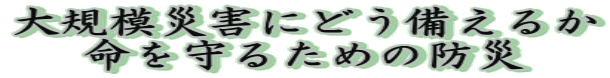
講師 片田 敏孝氏
群馬大学大学院理工学府教授
群馬大学広域首都圏防災研究センター所長
涙あり、笑いあり、また、歌にまで聞き入り、あっという間の2時間でした。
命を守るために最も必要なことは「率先避難の勇気」とその準備だということを
「共感のコミュニケーション」を通して、伺いました。
全国を駆け回りご活躍中の片田先生がお忙しい中、
当会講演会講師をお引き受けくださいましたことを改めて深く感謝いたします。
この聴講ノートは講演内容を元に国際交流まくはりが責任編集いたしました。
日時 平成28年(2016年)
1月31日(日)10時〜12時
場所 幕張公民館 参加者90名 参加費無料
主催 国際交流まくはり
後援 千葉市教育委員会 千葉市国際交流協会
- 率先避難者たれ!
- 東日本大震災において、釜石の小中学校では約3000人の子供たちが津波から避難し、全員無事でした。
- 先の大震災では子供を含め多くの犠牲者が出た中で、これは「釜石の奇跡」と呼ばれました。
- 「大きな防潮堤があるから逃げない」と言っていた子供たちに、10年前から釜石市の防災・危機管理アドバイザーとして、
- 「津波てんでんこ」という、生き抜くための防災教育を施された片田先生をお迎えし、
- 大規模災害にいかに備え、生き抜くかについて伺いました。
1. 防災とは何か・災害とは何か
命を守るための防災とは「いかに逃げるか」ということ。
防災は地域を守るマネジメントをディフェンスとオフェンス的な視点から行う。
- オフェンス : 公園、道、防波堤、高台避難所を作る
- ディフェンス: 災害時の自己防衛、意思疎通、身の回りの備え
アマゾンの奥地で河が氾濫してもそれは自然現象。
人が住み、社会を構成し、それらがダメージを受けるから災害なのだ。
2. 人間災害社会工学
人為的に作り上げる安全はヒューマンファクターの脆弱性が内在する。
- 設備(ハードウェア)や、他の誰かが守ってくれると思ってしまう子供が育つ。
- リスクに立ち向かう、自分の命を守るという感覚が乏しくなる。
「人間災害社会工学」とはこういう現状を危惧し、社会の安全、地域の安全を人間側からアプローチする学問。
単なる学問探究ではなく、社会をどう変えて行くかを考える。
3. 2000年代初頭から多発する自然災害とその巨大化
気象災害: 台風、竜巻、豪雨、洪水、雪害・・・いずれも巨大化、頻発化
- 1934年室戸台風911mb ⇒ 2005年カトリーナ・ハリケーン902mb
- 海温が上昇しており、今後850mb級の台風が予想される。
地象災害: 4つのプレート(太平洋、フィリピン、ユーラシア、北米)がぶつかり、ひしめき合っている日本列島では、
東日本大震災時、太平洋プレートが北米プレートの下に潜り込み、4枚のプレート間バランスが崩れたが、
現在そのバランスの補正期に入っている。
災いに備え、やり過ごす主体的な姿勢を保ちながら、今できることを粛々と行う。
自ら最善を尽くすのみ。
4. リスクに凛と向かい合う
2012年内閣府 東海・東南海・南海地震の想定震源域を想定(M9.1 1回/1000年)
南海トラフの巨大地震モデル検討会(2時検討会)による津波の高さを想定
想定の変更を受けて
尾鷲の80才の高齢者「17mの津波が来ると言うのは本当か」
⇒ 「その可能性はあるが、1000年に1度の確率であり、3000年に1度かもしれない。
80才ならお迎えが先に来る。安心して普通に生活しなさい」
- 死亡者 交通事故 400万人/1000年 (4000人/年)
- 地震 2万人/1000年
高知県黒潮町(予想される津波の高さ34m = 日本一)⇒元々日本で一番高い津波が来る地域。
⇒ 「何mでも同じである。自分たちは日本一の津波に向き合うぞと開き直ってはとうか」と助言
⇒ 缶詰工場を作り、缶詰に34mと表示。
自分の町に誇り。住民は3日に1回缶詰を食べ、とても元気になっている。⇒詳しくはこちら
想定が変わったことで住民が怯えはじめたが
想定が変わっただけで、自然や地球の営みが変わったわけではない
防災の実効性は人の行動規範にある ⇒ 避難所、設備を作ることばかりではない
地域は運命共同体。生きることには常にリスクが伴う。そのリスクに「凛」と向かい合う。
5. 防災教育とは「防災に向かう姿勢の教育」のこと
1) リスクだけを強調する防災教育はおかしい
- 親は子供たちにおびえる見苦しい姿を見せるな、語るな。
- 海は怖い所ではない、怯えているのは間違い。怖いのは地震の時だけ。
- 親が怖がれば、子供たちは海や町が嫌いになる。
2) 過去の教訓を生かせ
- 日本の歴史は津波の歴史。釜石には34基の碑。今回35基目。概ね100年の間隔。
- 自分が生まれる前のことはよく分からないものだ。神戸の子供たちに阪神淡路大震災のことを話しても伝わりにくい。
- 子供たちはまだ生まれていなかった。昔のことを言っても無理。
- 釜石でも震災前に子供たちに「釜石にあれだけ碑が沢山あるのは何故か」と話した。
- 津波が来ても誰も逃げなかったということだ。過去の教訓が生かされていないということ。
3) 「100回逃げても、それでも101回逃げてね」(釜石35基目の碑文)
- 津波警報はほぼ県単位で出される。そのため、対象地は広い。
- ピンポイントのところはそれでもよいが、実際、空振りの所が多い。
- 逃げて損したと言う感覚になる。となると、警報が出ても逃げなくなる。
- しかし、最後に1回的中する・・・
- 逃げて損したというよりは、逃げたけれど津波が来なくて良かったねということを習い性となす。
-
4) 釜石の奇跡
- 2011年3月11日14時46分 東日本大震災
- 死者115,885人、行方不明者2,623人、合計18,508人(関連死を含めて2万人)
釜石市鵜住居(うのすまい)地区
- 1896年 明治三陸津波 死者4,000人(人口6,500人) 堤防に安心して逃げなかった。
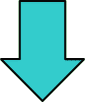
2011年 16mの津波(遡上高20m) 死者888人 関連死103人 行方不明152人 計1,143人
- 釜石小学校、釜石東中学校では、在校生と住民約3000人がとにかく逃げて無事だった。
率先避難を支援する訓練
- 防災教育は継続して行くことが重要
- 災害に備えることが当たり前という文化を醸成する
- 「僕は逃げるもん」という内発的な子供を作る
釜石では2011年3月11日に16mの津波。
- 川の氾濫と違って、津波は沖合での高さと同じ高さで寄せてくる。
- そして、それが引くときに海に引きずり込まれる。
- 高齢者を中心に多くの犠牲を出したが、子供たちは全員生き残った。この子供たちが次の釜石を作る。
事前に津波訓練。常日頃から、中学生が保育園まで行って子供の世話。
- おばあちゃんが高台までうば車につかまって上がるのを手伝っていた。
- お兄ちゃんお姉ちゃんが逃げろ逃げろと叫びながら逃げたので、子供たちも後を追った。
- それを見てコミュニティーが逃げた。
6. 共感のコミュニケーションから生まれる率先避難の教育
1) 人を変え、社会を変えるにはコミュニケーションの中に共感が必要
- 家具を固定しておく必要を伝えるにも、共感を伴うコミュニケーションが必要
- 例えば、母親が家具の下敷きになって動けないとき、「津波が来る、逃げろ」と言われたらどうするか、
- また、自分が下敷きになってしまったら、母親に何と言うかということから、
- 家具は固定しておかなければいけないと、伝える。
2) 津波てんでんこ(津波が来たらてんでんばらばらに逃げる)
- 避難所も大切だが、その前に心だ。自分の命を投げ出して家族を助けようとする心が時に命を奪う。
- 地震があれば、家族が一人一人で逃げることを話し合い、信じ合っておく。
-
- 逃げる場所を3か所くらい決めておく
- 家族は皆それぞれ自分で逃げるのだから、探しに来るな
- 子供は逃げた場所に止まっていれば、必ず父母が迎えに行く
-
- 率先して逃げるという決断には勇気がいる。
- 自分だけが助かればよいのかという後ろめたさに囚われず、まずは率先避難者たれ!
- 10年後、20年後、30年後に率先避難者たる市民を作る、親を作る、そういう社会を創るのには教育しかない。

-
千葉市議会議員の先生方、千葉市防災管理課・危機管理課、また、各地域の自治会関係者の皆様のご参加を得て、
お陰様で実り多い講演会になりました。
この講演会開催のためにお力添え下さいました千葉市防災管理課、幕張公民館、千葉市国際交流協会はじめ、
皆様に厚く御礼申し上げます。


![]()
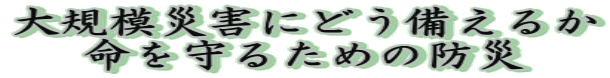
![]()